喘鳴患者の初期診療のポイントは喘息と心不全軸にする。
酸素とNIVを準備しつつ、身体所見とPOCUSで絞り込む。
レントゲンは“答え合わせ”である。
寒くなってきた。。。夜間帯の救急外来。
ストレッチャーが勢いよく搬入され、モニターが鳴り始める。
「53歳、男性、急な呼吸困難。喘鳴あり。SpO₂ 82%。搬送中も悪化傾向で酸素投与中です。」
救急隊の説明はそれだけ。
患者は前傾姿勢で肩呼吸、顔は蒼白。
ふと視線を落とすと、両下腿には――「浮腫…かもしれない」程度のふくらみ。
しかし、既往歴をゆっくり聞いている余裕はない。
とはいえ、“喘鳴があるから喘息だろう”と決め打ちするには危険すぎる。
喘息発作か、高血圧性急性心不全か?
どちらも「急激に悪化する」「喘鳴が出る」「低酸素になる」。
どちらも初動が遅れれば転帰に直結する。
そして何より、両者に共通する治療はすぐ始められるが、分岐点の治療が真逆である。
ここからの“最初の10分”が救急医にとって勝負となりやす。
ERで喘鳴が聞こえたとき、まず考える2つの軸。
【軸①】気管支喘息発作(± COPD増悪)
【軸②】急性心不全(とくに高血圧性急性肺水腫)
●喘息発作
主訴としての喘鳴なら、若年〜中年ではやはり頻度1位。喘息既往、アトピー・アレルギー体質、季節性・誘因のはっきりしたパターンが多い。
●急性心不全
「思っている以上に多い実質2位」。高齢者では、喘鳴の原因としてむしろこちらが多い印象すらある。特にACS関連心不全かどうかは、早めにチェックしておきたい。
さらに、頻度は落ちるが、絶対に忘れてはいけない“怖い”やつら:
・COPD急性増悪(既往、喫煙歴>40 pack-year、感染・気候変化)±気胸
・上気道閉塞(喉頭蓋炎、声帯浮腫、異物)
→ wheezeというよりstridor。生命危険度はここが最凶。
・肺塞栓(胸痛・頻脈・低酸素+喘鳴=PEは意外とある)PMID: 14676506
・アナフィラキシー(全身症状+ wheeze)
・気道内腫瘍・声帯麻痺(慢性の“片側性喘鳴”に注意)
~2分:患者がERに入った瞬間に走らせる「共通初療」
搬入されたら、まずはABCD。
蘇生レベルなら迷わず蘇生を優先――これは大前提。
そこまでクリティカルでなければ、患者がストレッチャーに乗った瞬間に、最低限この3つだけは指示する。
➀ 酸素投与(マスク or リザーバー)
低酸素は、喘息でも心不全でも確実に悪化因子。
COPD増悪のCO₂ナルコーシスは気にはなるが、低酸素の放置は“厳に慎むべき”病態である。
モニターをつけたうえで、呼吸様式(努力呼吸か、呼気延長か)、呼吸数、SpO₂を見ながら、必要な分だけしっかり酸素投与を行う。落ち着いたら FiO₂は引き算していけばよい。
② NPPV(CPAP/BiPAP)の準備
これは両者に共通して有益。
心不全:死亡率と挿管率を下げることが複数のRCT・メタ解析で示されている。
喘息:呼吸仕事量を減らし、挿管を回避し得る(適切な設定なら安全性も高い)。
「NPPVを“いつでもかけられる状態”にしておくこと自体が救命手技の一部。
実際に装着するかどうかは、このあと数分で判断する。
③ 末梢ルート確保
ただし輸液は入れない。まずキープ程度。輸液の選択は何でも良いが、詳しくは別記事で。
➡「輸液どれにします?」って聞かれて「とりあえず、生食」と答えてしまう、あなたに。輸液選択で知っておくべき3つのこと – 救急医の頭ん中。
心不全にも、喘息の胸郭負荷にも不利だから。
この時点では、まだ鑑別はついていない。
しかし、両者に不要な遅れはゼロにしておく。
つまり 「共通治療を先に走らせ、その間に鑑別を進める」 という時間設計で動く。
~5分:身体所見+POCUSで、ほぼ鑑別をつける
ここからが本丸。
“身体所見+POCUSで、レントゲンを待たずに勝負をつけにいくフェーズ” である。
① 既往と発症様式
- 喘息・COPDの入院歴
- 冠疾患・心不全・高血圧・腎不全
- 「何分でここまで悪化したか?」
数分〜数十分で急激に悪化 → flash pulmonary edema:高血圧性急性心不全のクラシック。
半日かけてじわじわ → 喘息・COPD増悪を支持。
もちろん感度も特異度も“ゆるい”指標ですが、「ベースの心血管リスク」と「スピード感」は、鑑別の事前確率を決めるうえで重要。
② 身体所見:ベッドサイドの“軽いLR”
- 血圧 180以上+冷汗 → 心不全の尤度UP
- 呼気延長+胸郭の大きな動き → 喘息を支持
- wheeze+crackles → “cardiac asthma”寄り(特異度が上がる)
crackles の感度は 60–70%、特異度 70–80% と強くはないが、「wheezeに“濡れた音”が混ざる」場合は心原性肺水腫が濃くなる。
*私は心雑音、特にASを疑う収縮期雑音は同時に聞くようにしてる(後述)
③ POCUS(肺・心・IVC)
ここで POCUSの一撃は、レントゲンより上 の診断性能を持つと思っている。
【肺エコー】
1肋間に3本以上のB-line → interstitial syndrome
10本以上で融合(confluent) → B-profile=肺水腫ほぼ確定
感度 90–97%、特異度 約90%。
心不全に限らず、肺炎・ARDS でも出るが経過/病歴と合わせると 「これが出たらほぼ心不全として治療してよい」と思っている。気胸のスクリーニングもお忘れなく。
【心エコー】喘息では、心臓は意外と“きれい”なことが多い
左室肥大+高血圧 → 心不全
壁運動異常 → ACS併存
*ASなどの弁膜症所見もざっとでいいので見ておく(後述)
【IVC】座位で評価することが多く、精度は落ちるが、小さな証拠を素早く積み上げる。
太くて呼吸性変動乏しい → volume overload:心不全
細くてつぶれる → 喘息や脱水寄り
これらを一通りざっと見るのに、慣れれば 1〜2分。
メタ解析では、心不全疑い患者に対するLUS併用評価は、CXRよりも高い感度(約92%)と特異度(約92%)を示し「レントゲンより先に、肺エコーを信じてよい」時代になりつつある。PMID: 35504747
この 5分で、ほぼ鑑別がつく。レントゲンはまだ到着していないが、気にしなくてよい。
5〜10分:目星をつけて「先に治療を切る」、レントゲンは答え合わせ
ここまでで、頭の中ではだいたいこう整理されているはず。
- 「心不全>喘息」
- 「喘息>心不全」
- 「どちらとも言えない(COPD増悪+HFとか)」
ちょうどこの頃、レントゲン技師さんがERに到着する――そんな世界線を想像してほしい。
A. 心不全優位と判断した場合
すでにNPPVは準備されているはずなので、
➀ CPAP or BiPAP を開始
高血圧性肺水腫なら、CPAP 4 cmH₂O から開始し、6–8 cmH₂O ➡ 許容できれば早々に10 cmH₂O まで、SpO₂・呼吸困難の改善を見ながら調整します。
しんどい患者さんにNPPVを装着する 30秒は本当に勝負だと思っている。前提として、患者は既に苦痛と不安でパニック寸前。そこに「見慣れない大きなマスク」「押し込まれる空気」。何も言わずつけたら、高確率で外されて終わる。だから、つける前に必ずこう声をかける。
「空気を押して肺に入れて、呼吸を楽にしてくれるマスクです。苦しいのを止める手伝いをします。最初だけ少し圧がかかり、びっくりしますが、すぐ呼吸が楽になってきます。目を開けて、僕の方を見て。息を合わせていきましょう。つけますね。」
“押しつける機械”ではなく、“助ける機械”であることを伝える。
これだけで、導入成功率はかなり変わる。
② ニトログリセリンによる前・後負荷軽減
血圧が十分高い(収縮期 140–160 以上)なら、
1:ニトロ経口 (舌下、スプレー:ニトロペン舌下錠0.3mg、ミオコールスプレー0.3mg)
2: ニトログリセリン(私は硝酸イソソルビドも使うことがあるが切れ味はニトログリセリンか…)を静注開始(血圧)し、血圧をモニターしながら調整します。
【硝酸薬の禁忌】右室梗塞(右室プレロード依存 → ショック化)・重度AS(大動脈弁狭窄)
PDE5阻害薬内服(シアリス/バイアグラ)12–48h以内・収縮期血圧 < 100
●ニトログリセリン(原液5mg/10ml・25mg/50ml)を側管(ここのメイン流量は注意)から投与。添付文書どおり「0.05–0.1 γ」だと、収縮期180のFlash肺水腫では“正直ぜんぜん効かない”というのが本音。僕は使うなら状態をよく見ながら 体重50 kgなら原液3 mL/hくらいから始める ことも多い。
●どちらかといわれると僕は硝酸イソソルビド(ニトロール®持続静注25mg/50ml)が好みだったりする。理由は動脈を一気に開く切れ味がないので血行動態の破たんリスクが低めであること、相対する論拠で申し訳ないのだが僕はセッカチ症候群を持病に持つため、「2mlフラッシュして時間6mlで開始して」などと指示をする。この「2mlフラッシュ(静注)して」効きが悪ければ「2mlフラッシュ追加してベース+2ml/hrに上げて」などと調整をしやすいとか静注しても下がりすぎることは少ないというのが即時の反応を求めてしまう僕の性である。
どの硝酸薬を使うにしても、モニタリング下で、患者の反応性を見ながら微調整することが肝。ASがありそうなら、僕は“とにかくゆっくり”を徹底している。
③ ループ利尿薬(フロセミド)は「後から冷静に」
volume overload が明らかなら併用。ただし「とりあえずフロセミド」ではなく、血圧・腎機能・IVC所見を見て投与量を考えます。
ここまでの治療は、胸部レントゲンよりも早く始めるべきです。
なぜなら、CXRでのうっ血所見は感度がせいぜい 54〜76% 程度であり、一方で特異度は高い(87〜95%)ものの、「陰性だから心不全ではない」とは全く言えないからです。
しかしながら、喘鳴を起こしているレベルの喘息・心不全なら経験上、まずレントゲンはbutterfly shadowでうっ血所見でしょうけど。
レントゲン結果は、「やはりbat-wing pattern/butterfly shadowで答え合わせ完了」「意外とうっ血が軽く、COPD+HFの可能性を考え直す」といった修正の道具として使う方が私の好みのストラテジーです。
B. 喘息優位と判断した場合
肺エコーがA-line主体、左室はきれい、IVCはむしろ細い――
このあたりが揃えば、心不全の事前確率を一段下げて、急性喘息として治療を切るのが合理的。
喘鳴のある喘息ならまだまし “silent chest” を頭の隅に考えつつ喘息治療に舵を切る。
このときも、酸素とNPPVの準備は共通ですが、薬物治療が変わります。
➀SABAの反復吸入(サルブタモール・プロカテロール等)
👉 「ネブ を10〜20分おきに反復」は、効果と副作用のバランスがとれたところ。
②全身ステロイド(メチルプレドニゾロン等)
👉 「来院してからウダウダ悩まず、急性増悪と判断したら早めにステロイドを打つ」ことで
・入院・再発・後のSABA使用量をまとめて減らせるというエビデンスがある。
PMID:10796685 PMID:22410507
③重症例ではMgSO₄静注
【SABA】吸入方向は噴霧式吸入器+スペーサーとネブライザーは同等の効果なので家で処方の吸入をしてきているのに改善しないのはうまく吸えていないか、比較的重篤かです。
僕の経験上で申し訳ないがERでは意外とプロカテロール(メプチン®)の使用が多いと思う。
最近ではユニットになっているので間違いは少なくなっているがメプチンの吸入液0.01%は30-50µg(0.3-0.5ml)である。3mlとか使用すると頻脈とかめまいとか副作用はえらいことになろう。注意。小児は10-30µg(0.1-0.3ml)が目安。
サルブタモール (ベネトリン吸入液0.5%)は濃度の違いはあるが液量は同様に0.3〜0.5mL(サルブタモールとして1.5〜2.5mg)、小児は1回0.1〜0.3mL(サルブタモールとして0.5〜1.5mg)。生理食塩水で薄めるがそれはネブライザーの特徴次第であり、個別に検討を。
【全身ステロイド】ここは【重要】救急外来でステロイドを使えるようになる!➀何のために、どのステロイド使うのか? – 救急医の頭ん中。を参考に。genomic effectを念頭に多くてもプレドニゾロン換算で約1 mg/kgまで。効果は数時間かかる。呼吸状態の重症度、消化管に問題なければ僕は血中濃度、アスピリン喘息という伏兵を考慮して内服を1stの選択にしている。内服はプレドニン30-60mgを目安としている。コハク酸問題は他で論じるとしてメチルプレドニゾロン(ソルメドロール)なら125mg、ヒドロコルチゾン(ソルコーテフ)は100mg*2=200mgを使っている。炎症を抑える意味でも研究で使い古されたという意味でも前者を使用することが僕は多いが薬の違いによって予後の差はないのが現エビデンス。あとは半減期、胎盤透過性を気にしつつ、リン酸エステル型という意味ではデカドロン6.6mgも吉。リンデロンはデカ様と似ていはいるが別にあえてこれを使おうとは思わない、使ってもいいが。
【MgSO₄静注】2 g IV を 20–30分で投与(標準)あくまで重症にしぼると効果がある。軽症に投与する必要はないと思う。
*ここはエキスパートオピニオンではあるが挿管レベルの喘息患者で循環動態次第ではエピネフリンの0.3-0.5mg筋注を試すこともある。ただ、正直なところ 「これで挿管を回避できた!」という手応えはそこまで多くない。「やることはやった」という意味合いに近い。
ここで注意すべきなのは、万が一心不全だった場合、β₂刺激薬は頻脈・不整脈・虚血を助長しうる点。しかし「身体所見+エコー」で心不全の事前確率を十分下げてから使うのであれば、そのリスクはかなり許容可能になります。
ま、どうしても鑑別つきにくければ1回くらいは許容して改善するか試すのも臨床的には大事な手段かなとは思うがそうゆう場合は焦らず、詳細病歴やレントゲンも検討を。
あとはBNPは、カットオフ 100 pg/mL で感度約 90〜95%、特異度 60〜75% 程度とされるのでそれも参考に。
上記の酸素投与、薬剤投与でも呼吸状態が芳しくない場合、意識が保たれて協力可能、収縮期血圧が保たれているのであれば、まずNPPVを試みるのが標準です。ここらへんで胸部レントゲンは出ているはず、エコーとレントゲンから気胸、肺炎は考慮出来ている。
それでも「10〜20分でSpO₂・呼吸困難・pHが改善しない」「意識レベルが低下してきた」「ショックになってきた」といった場合は、挿管に踏み切りる。
重症喘息:挿管は「避けたい」が「遅らせていい」わけではない
呼吸上状態が悪いのでリスクを鑑みて「早々と気管挿管・人工呼吸器管理しておこう」という対応がしにくいのが喘息。なぜなら「挿管時に心停止リスクのある」「挿管した瞬間に病態が一気に難しくなる」疾患だからですね。
●ダイナミックハイパーインフレーションで管理上、胸腔内圧が高くなるので純粋な陽圧換気は循環虚脱を起こしやすい。脱水も合併していることも多く、それも相まって挿管時に血圧下がる。
●auto-PEEPで換気しにくく悪化する。
●挿管難易度も高く、自発呼吸を消して自身の努力呼吸を止めて挿管手技を始めてしまうとCICV(Can’t Intubate, Can’t Ventilate)リスクが高く、挿管できても換気が出来ず心停止などというストーリーも十分に考えられる
●そもそも気道の中にtubeが入っている刺激自体が喘息を悪化させる➡人工呼吸器管理も長期化する傾向がある
以上から、できれば気管挿管を回避したいのです。
しかし、気管挿管は回避はしたい=遅らせるではありません。
対応が遅れれば死ぬ+適切なタイミングが極端に狭いのが難しいポイント。
したがって、SABA、ステロイド、MgSO4、NPPV、ケタミン、±エピネフリンなどをやりつつ
・酸素化、呼吸数の低下
・反応性低下・疲弊(silent chestへ)
・PaCO₂の上昇とpH低下
・NPPVを試せない・拒否するほどの不穏
・意識障害
など、「明確な限界を超えた」と判断した時点で初めて挿管すべきです。
挿管は、Difficult Airway Managementをフルセット準備の上で RSI。
僕は以前「自発を残して挿管できないか」と考えていた時期もあるが、エビデンスや経験からも ケタミン(1–2 mg/kg)+ロクロニウム(1–1.2 mg/kg)で一気に挿管 が推奨されると思っている。
【人工呼吸器の設定】
低PEEP、低呼吸回数(8〜10回/分)、長い呼気時間(I:E比=1:4)、許容高CO₂(permissive hypercapnia:pH7.2くらい)を意識してセットします。一回換気は6ml/kgで開始して調整、A/Cで従量式でも従圧式でもよいが、僕は従圧式(PCV)でどの圧で換気がどれくらい入るか慎重にみつつalarmとの相談をしている。あとは深めの鎮静(+ ケタミン)。
挿管直後は 「かなり恐る恐る」 のフェーズで、ピーク圧ではなく plateau圧 を気にしながら、少しずつ調整していく。
最後に:喘鳴の患者がERに来たときの「今日の処方箋」
軸はシンプルに:まず「喘息 vs 心不全」で考える。
その他のヤバいやつ(上気道閉塞・PE・アナフィラキシー)は常に頭の片隅に。
酸素とNIVを準備しつつ、身体所見+POCUSで3〜5分以内に事前確率を大きく動かす。
レントゲンは「診断の起点」ではなく「答え合わせと修正」の道具。
心不全なら:CPAP+ニトロで“圧を抜く”のが主役。利尿薬は後から。
喘息なら:SABA+ステロイド+必要ならMgSO₄。
β₂刺激薬を打つ前に、POCUSで心不全の確率をきちんと下げる。
重症喘息の挿管は、“できれば避けたいが、必要なら一秒も迷わない”。
そのために、挿管前にやれることをすべてやりつつ、
「ここを越えたら挿管」というラインを自分の中にはっきり持っておく。
そして何より、最初の10分を“意図して設計する”。
「とりあえず酸素」「とりあえずレントゲン」ではなく、
“共通治療を走らせながら、POCUSで鑑別を詰めていく10分” を、意識して過ごす。
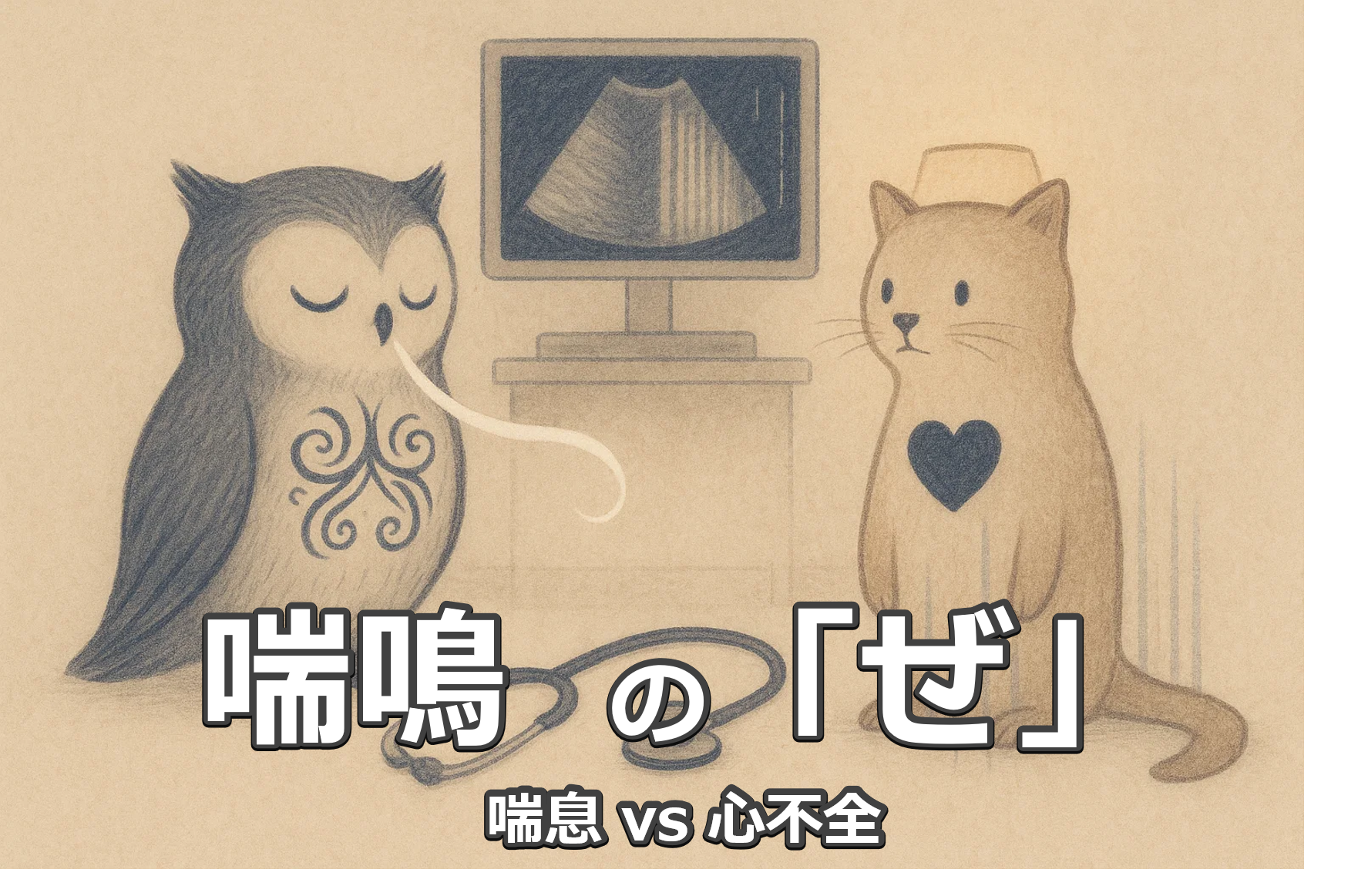
コメント