若人に中心静脈カテーテル挿入のちょっとしたレクチャーをした。人のふりして我が振りなおせ。
改めて自戒の念を込めて。
0. 導入 ― 中央ラインは「誰でも挿せる」時代?いいえ、「挿せる+安全が必須」の時代です
救急外来やICUでは、中心静脈カテーテル(CVC)は酸素投与や気管挿管と並ぶ“ライフライン”の一つ。高濃度カリウムの迅速投与、昇圧薬の持続投与、大量輸血―これらを安全に行うには、末梢ルートでは不十分になる場面が少なくない。
しかし「刺さったから終わり」ではなく、正確な適応判断・合併症の予防・抜去まで一気通貫でマネジメントする力こそ、急性期医師、看護師に求められるコアスキル。
国内外の報告によれば、CVC関連血流感染(CLABSI/CRBSI)はなお ICU の院内感染の最大因子であり、患者死亡率・入院期間・医療費を顕著に押し上げています ☞NCBI ☞日本麻酔科学会。
日本麻酔科学会が示す「プラクティカルガイド」は、無菌環境の徹底や超音波ガイド下穿刺の標準化を強く推奨し、シミュレーション教育を必須項目として掲げてる。
さらに JCQHC(患者安全推進協議会)はチェックリストの活用を明文化し、エラーを“人の注意力”ではなく“システム”で潰す設計思想を打ち出しました。
一方、海外レビューは“US first, wire second”の六段階アルゴリズムを推奨し、胸腔損傷や動脈誤穿刺は 90 %以上削減可能と報告しています。
つまり、エビデンスは「精度」と「安全」を同時に高められることを示しています。本シリーズでは、
- 適応と禁忌を瞬時に見抜く判断フレーム
- セリディンガー法&超音波ガイド下の手技
- CLABSI/CRBSI ゼロを目指す感染制御バンドル
合併症を“診断”ではなく“予防”するアプローチ
小児・ECMO・PICC など特殊症例の勘所
を、ガイドラインと現場ナレッジを“統合”した形で解説します。
図解・動画リンク・チェックリスト完備の“再読に耐える備忘録”として、ERでもスマホ片手に即復習できる構成を目指してみました。分量は多いかなW
読後ゴール
- 挿入前 30 秒で“サイト・カテ種・長さ”を言語化できる。
- エコー画像を 1 枚見た瞬間に“刺入角度と深さ”を決められる。
- カテ挿入後の X 線で「先端がズレている」ことに 5 秒で気付ける。
- CLABSI 率をゼロに近づけるプロトコールを自施設で実装できる。
さあ、“刺せて当たり前”の先へ――安全と質を両立する CVC マスターへの道を、一章ずつ歩んでいきましょう。
おまけの【実践パール】
- 「刺す前に目的を3秒で言語化せよ」
CVCは侵襲的。適応を言葉にできない時点で、それは“不要な手技”かもしれない。
(参考:JSA Practical Guide 2017)
- 「エコーは穿刺よりプリスキャンが本番」
針を刺す前にメルクマールと解剖を視診、エコーで特定し、角度と深さを決める。戦略8割、実行2割。
(参考:BioMed Central 2017, StatPearls)
- 「内頚で迷ったら“黒くてつぶれる方”を刺せ」
超音波で確認。頸動脈はつぶれず、拍動が強い。静脈はつぶれる。外側に静脈。基本だが命綱。
(参考:Ultrasound Review, StatPearls)
- 「穿刺時に一瞬“ビヨッ”と戻るのは動脈」
細く速く、拍動性が強く赤ければ動脈。静脈は戻りがゆっくり。
(参考:McGee DC et al. NEJM 2003)
- 「ワイヤーが動かない=“壁に当たってる””kinkしている”と疑え」
無理に進めない。血管を突き破るリスク大。(参考:StatPearls)
- 「鎖骨下は刺す角度でが命」
気胸のリスクが高い部位。針は鎖骨に沿わせるように浅く。(参考:BioMed Central 2017)
- 「大腿は使っても、居座らせるな」
感染率が他部位の3倍。緊急用で、状態安定後はRIJやSCVへ切替。(参考:CDC Guidelines 2011)
- 「感染は“運”じゃない、“時間”と“触れた回数”」
ドレッシングの剥離、ルーメン使用回数、留置日数のすべてがリスク。
(参考:CLABSI対策バンドル, JECCM 2023)
- 「ロック剤の効果より、パージの丁寧さ」
“流れ”を残すパージの方が、血栓・感染の予防に効くことが多い。
(参考:Goossens GA. Nursing Research and Practice 2015)
- 「CVPは“数字”でなく“波形と変化”を読むもの」
絶対値はあてにならない。脱水?圧迫?波形から背景を読み解く技量が問われる。
(参考:Marik PE. Chest 2008)
- 「抗菌コーティングは魔法ではない」
使いどころが大事。長期留置・感染リスク高い症例限定で。
(参考:CDC Guidelines 2011)
- 「CVカテを使い回すと、必ず“誰かが泣く”」
“とりあえず残しておく”が感染・血栓・誤用の温床に。(現場経験・臨床合併症から)
- 「シリンジ接続時に“airを感じ”がしたら、即シール確認」
接続の緩みやクランプ開放が空気塞栓につながることもある。
(参考:JCQHC チェックリスト 2020)
- 「CV先端は右房に“入らない”ことが重要」
右房まで入ると不整脈や心タンポナーデのリスクが高くなる。SVC止まりが原則。
(参考:BMC 2017, JSA Practical Guide)
- 「PVCが出たら“心臓に触れている証拠”」
ワイヤーやカテが心房内に迷入している可能性。すぐに位置調整。(参考:StatPearls)
- 「小児では1mmのズレが“致命傷”になる」
体格が小さく、構造も脆弱。成人の“誤差”が致命的になる。
(参考:Walker G et al. Br J Anaesth 2018)
- 「穿刺抵抗が変わったら、1mmでも引いてから再確認」
“スッと”入っていたものが途中で止まったとき、それは危険信号。
- 「CVを抜くときは“頭を下げ、息を吐け”」
空気塞栓予防の基本。Trendelenburg位+呼気時抜去を徹底。
(参考:CDC Guidelines 2011)
- 「固定は“美観”ではなく、“感染制御”である」
ズレない・濡れない・蒸れない固定がドレッシング感染を防ぐ。
(参考:CLABSI Bundle, CDC)
- 「ログがない手技は、“経験”にならない」
自分の失敗や成功を記録してはじめて、技術は“再現性”を持つ。
(参考:JSA 教育指針)
- 「1人の上手さより、チーム全員の安全文化」
誰かだけができる状況では、事故は必ず起きる。仕組み化が命を守る。
(参考:WHO Patient Safety 2009)
- 「ピアレビューは“ダメ出し”ではなく“未来出し”」
技術の点検は、“改善の種”を見つけるために行うもの。
- 「CheckはToDoでなく、“予防のアクション”」
チェックボックスを埋めるだけではなく、リスクを潰す行動に意味がある。
(参考:JCQHC チェックリスト)
- 「シミュレーターで笑えても、現場では笑えない」
安全に“失敗できる場”での準備が、現場での事故を防ぐ。
(参考:Froehlich CD et al. Pediatrics 2011)
- 「“あれ?何か変”が最も貴重なサイン」
直感的な違和感は経験の蓄積。軽視せず止まる判断を。
- 「“CVあるから安心”が最も危険」
“ある”こと自体は安全ではない。適切に“使える”ことが重要。
- 「感染サインがなくても、“15日目のCVは疑え”」
感染は無症状から始まる。期間が長くなるほどリスクは上がる。
(参考:CDC, BMC 2017)
- 「CVのベストポジションは“入れた人”より“現場の皆”が知っている」
先端位置や使用状況は、時間とともに変化する。チームで追うべし。
(マルチディシプリナリー管理より)
- 「技術の先に“人間がいる”ことを忘れるな」
手技の成功ではなく、“その先の患者”を見つめる視点が本質。
- 「CVCは“器用さ”ではなく、“誠実さ”の技術である」
細かな作法の積み重ねこそが、安全なCV管理につながる。
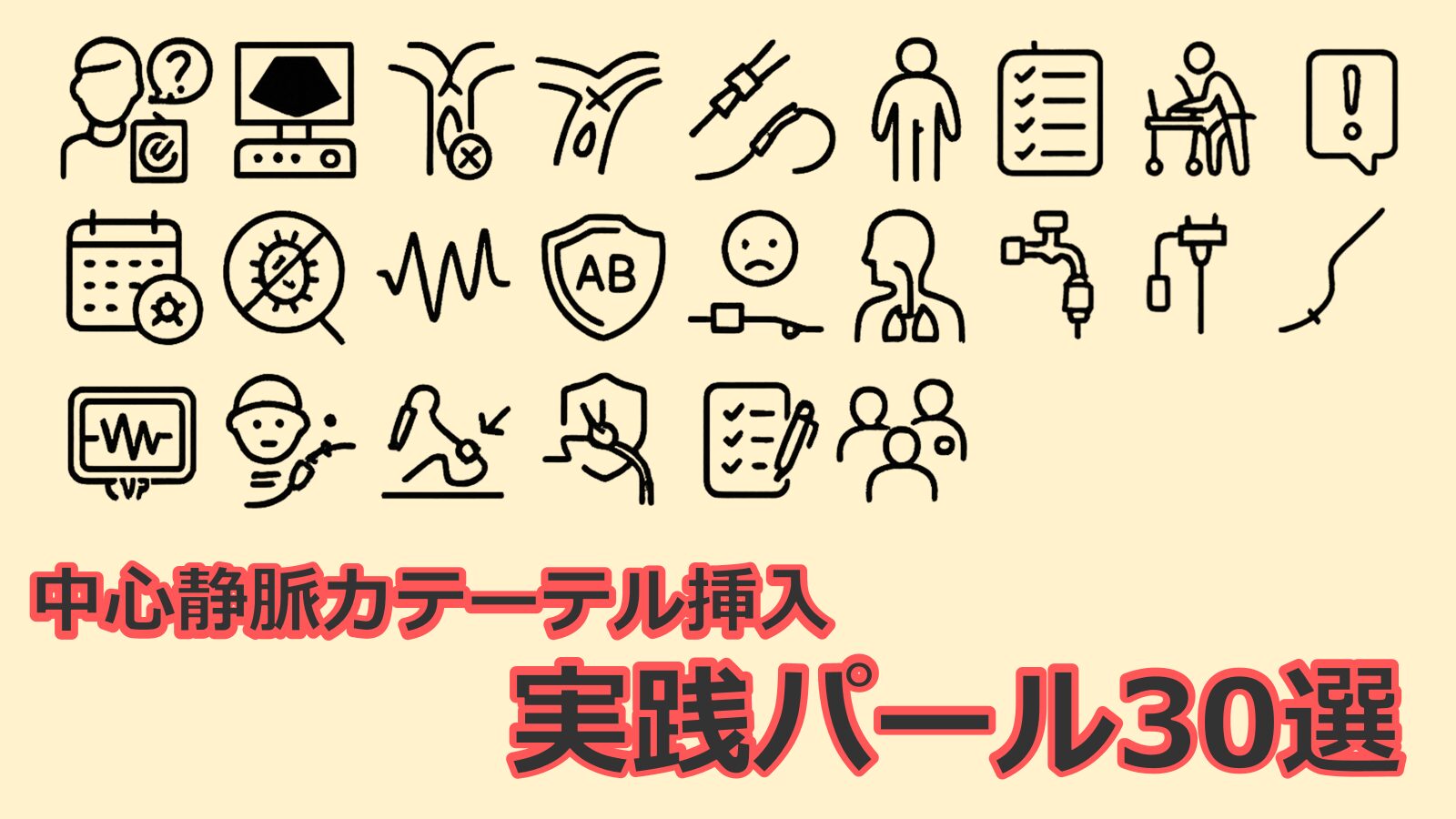
コメント